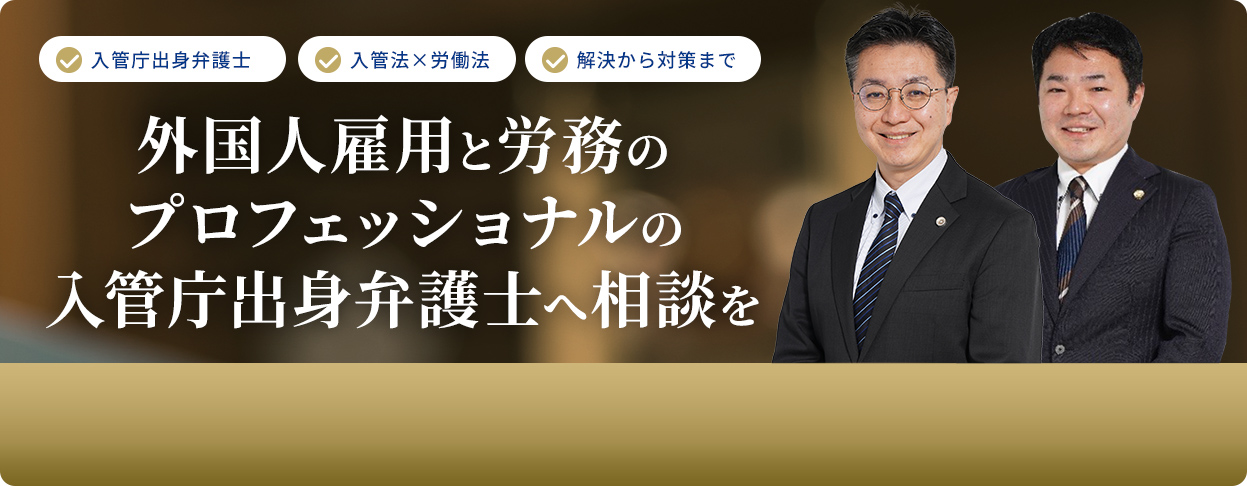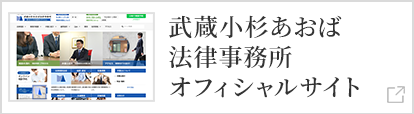目次
1. 監理団体とは
技能実習制度を活用するために理解する必要があるのが、監理団体という団体の役割です。
監理団体とは、海外での技能実習生の募集、受入に際して必要な各種手続きを行う組織のことを指します。
技能実習生の受入には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類の方法がありますが、団体監理型にて技能実習生を受け入れる場合、監理団体の関与は必須になります。現在多くの技能実習生が団体監理型によって受け入れられており、監理団体のニーズは高まっています。
2. 監理団体設立のための要件
そもそも監理団体の許可を得るために要件があるため、その要件を満たさなければ監理団体としての資格を得ることはできません。
監理団体の許可基準については、技能実習法によって定められており、主な要件は下記の5点になります
- a. 営利目的ではない法人であること(事業協同組合、公益社団法人など)
- b. 監理事業を適正に行うに足りる能力があること
- c. 監理事業を遂行できる財産的基礎を持っていること
- d. 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
- e. 外部役員または外部監査の措置を実施していること
3. 監理団体設立の流れ
監理団体は非営利組織である必要があるため、まずは非営利組織である事業協同組合の設立から始めることが一般的です。そのため設立の流れとしては①事業協同組合の設立②事業協同組合の登記③監理団体許可申請という手順になります。
① 事業協同組合の設立
事業協同組合設立は以下のような流れで進めます。
① 設立発起人の選定
事業協同組合の設立には、まず設立発起人が4名以上必要です。設立発起人は事業主(法人又は個人事業者)である必要があり、その他にも資本金額、従業員数の基準を満たす必要があります。
② 発起人会の開催と基本事項の決定
発起人が確定したら、発起人会を開催し、事業協同組合を運営していく上での必要事項を決めていきます。具体的には、定款案、事業計画や収支予算書の作成、代表発起人の選出など、いずれも事業協同組合を運営していく上での必須事項になる事項を、発起人全員で確定させていきます。
③ 創立総会
発起人会にて作成した定款や事業計画等を確定させ、理事や監事の選挙などを行う場となります。この総会において発起人たちの間で意見をすり合わせ、最終確定とすることがトラブルやもめごとを減らすためには大切です。
④ 設立認可申請
総会にて必要事項を確定させた後、各所轄の省庁へ設立許可申請を行います。認可申請が認められるまで、約3~4か月程度かかることが一般的です。
②事業協同組合の設立登記
出資金を出資者がそれぞれ払い込み、出資の払込があった日から2週間以内に、事業協同組合の設立登記を行う必要があります。登記は、各管轄の法務局に行ってから行うため、それぞれの地域でどこの法務局に行く必要があるか調べておくとスムーズです。
③監理団体許可申請
登記まで完了して初めて、監理団体としての許可申請を行うことができますが、この申請は煩雑なものになるため、行政書士など法律に精通した士業事務所へ依頼をすることが大切です。
これらすべての申請を終了し、監理団体として認められるまでには、約1年程度の期間を要します。そのため、設立を検討される場合は申請開始から許可が下りるまでの期間も検討する必要があります。
4. 監理団体設立のメリット
監理団体を設立すると、以下のようなメリットがあります。
1.法令遵守の徹底とリスク軽減
監理業務を監理団体に委託していた場合でも、外国人の雇用・労務管理に関し法令違反が発生した場合の責任は最終的には受入企業が負うことになります。しかし、自社で監理団体を設立することで、入管法や技能実習法に精通した顧問などの設置をすることにより、自社や監理団体の組合企業において、法令違反のリスクを減らした状態で、技能実習生を受け入れることが可能になります。
2.コスト削減と新たな収益源
監理団体に支援業務を委託する場合、技能実習生1人当たり約3万円程度の管理費が必要になります。自社で監理団体を設立することによって技能実習生の監理費用を軽減することができます。また、組合員を増やし、監理業務をより多くの企業に行っていくことで、監理費の徴収も可能となります。
3.特定技能への円滑な移行と安定した継続雇用
技能実習から特定技能への移行・雇用継続を行う場合には、受入企業は支援業務を行う必要があります。この支援業務と監理事業については共通する箇所も多くあるため、自社において支援業務を内製化できている場合、技能実習から特定技能への移行、及び継続雇用がよりスムーズに実現できます。
5. 当事務所のサポート内容
監理団体を設立したいと考えた場合に、
- 書類作成ノウハウがない
- 申請の手続きの流れがよくわからない
といったお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、監理事業の許可申請業務だけではなく、監理団体として事業を開始された後、外部監査の実施、日常の運営に関するご相談対応、入管当局からの改善勧告や許可取消処分への対応など、継続的なサポートが可能です。外部監査役や外部役員として就任し、法令遵守体制の強化や適正な運営を支援することで、監理団体の持続的な発展に貢献いたします。
6. 監理団体の設立・運営については、当事務所までご相談ください
事業協同組合の設立や監理事業の許可申請には、多岐にわたる書類の準備や煩雑な手続きが伴い、通常業務と並行して行うには大きな負担となります。
当事務所では、監理団体の設立をご検討されている皆様からのご相談を承っております。入国管理局出身の弁護士が、その専門知識と豊富な経験に基づき、皆様のご希望に沿えるよう親身にサポートさせていただきます。
特に、設立後の外部監査や、入国管理局との折衝・対応においては、他の事務所にはない強みを発揮いたします。
監理団体の設立や運営に関し、ご興味をお持ちの方、お困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。