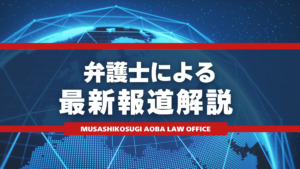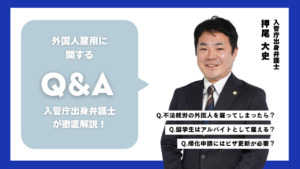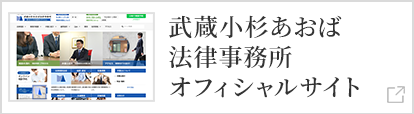-
2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクトについて弁護士が解説
 2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクト
― 登録支援機関・企業は何を変えなければならないのか ―
外国人材の受入れを行う企業にとって、「登録支援機関に任せておけば安心」という時代は、2026年を境に大きく転換点を迎えます。
2026年1月施行の行政書士法改正は、登録支援機関の業務範囲、報酬の取り方、そして企業側の法的責任にまで直接影響を及ぼす内容だからです。
本コラムでは、改正の趣旨を踏まえつつ、これまで“慣行”として行われてきた実務が、なぜリスクになるのか、そして今後どのように是正すべきかを、弁護士の立場から具体的に解説します。
…
2026.01.05
コラム・法改正情報最新報道
続きを見る »
2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクト
― 登録支援機関・企業は何を変えなければならないのか ―
外国人材の受入れを行う企業にとって、「登録支援機関に任せておけば安心」という時代は、2026年を境に大きく転換点を迎えます。
2026年1月施行の行政書士法改正は、登録支援機関の業務範囲、報酬の取り方、そして企業側の法的責任にまで直接影響を及ぼす内容だからです。
本コラムでは、改正の趣旨を踏まえつつ、これまで“慣行”として行われてきた実務が、なぜリスクになるのか、そして今後どのように是正すべきかを、弁護士の立場から具体的に解説します。
…
2026.01.05
コラム・法改正情報最新報道
続きを見る »
-
外国人の国民健康保険料未納者への在留審査厳格化について弁護士が解説
 外国人の国民健康保険料未納者への在留審査厳格化(2027年6月開始予定)について
――企業の外国人労務管理に求められる対応――
2025年11月4日の記者会見において、上野賢一郎 厚生労働大臣は、外国人による国民健康保険料の未納防止策を2027年6月から開始する方向で準備を進めていることを明らかにしました。
本稿では、制度の概要と、雇用主に想定される実務上の影響について解説します。
政府が示した対策の概要
(1) 保険料未納者には在留資格の変更及び期間の更新を原則認めない仕組みへ
厚生労働省は、出入国在留管理庁と連携し、国民健康保険料の滞納情報を在留審査に反映さ…
2025.11.18
コラム・法改正情報最新報道
続きを見る »
外国人の国民健康保険料未納者への在留審査厳格化(2027年6月開始予定)について
――企業の外国人労務管理に求められる対応――
2025年11月4日の記者会見において、上野賢一郎 厚生労働大臣は、外国人による国民健康保険料の未納防止策を2027年6月から開始する方向で準備を進めていることを明らかにしました。
本稿では、制度の概要と、雇用主に想定される実務上の影響について解説します。
政府が示した対策の概要
(1) 保険料未納者には在留資格の変更及び期間の更新を原則認めない仕組みへ
厚生労働省は、出入国在留管理庁と連携し、国民健康保険料の滞納情報を在留審査に反映さ…
2025.11.18
コラム・法改正情報最新報道
続きを見る »
-
海外にいる外国人を採用する場合の注意点はなんですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
海外在住の外国人を採用する場合、以下の点に十分留意する必要があります。
解説
在留資格適合性の確認
海外在住の外国人を採用し、日本で働く場合、何らかの在留資格が必要となります。在留資格は、日本で従事する活動内容に着目した活動資格と日本での地位又は身分に着目した身分資格に分類されます。活動資格の場合、在留資格ごとに日本で従事することができる活動の範囲が定められています。そのため、現地での採用に際し、あらかじめ求人内容(日本での業務内容)と予定される在留資格との適合性があるかを確認することが必要です。在留資格で認められる範囲を超えた業務に従事させた場合、雇用主は不法就労助…
2025.10.28
続きを見る »
弁護士からの回答
海外在住の外国人を採用する場合、以下の点に十分留意する必要があります。
解説
在留資格適合性の確認
海外在住の外国人を採用し、日本で働く場合、何らかの在留資格が必要となります。在留資格は、日本で従事する活動内容に着目した活動資格と日本での地位又は身分に着目した身分資格に分類されます。活動資格の場合、在留資格ごとに日本で従事することができる活動の範囲が定められています。そのため、現地での採用に際し、あらかじめ求人内容(日本での業務内容)と予定される在留資格との適合性があるかを確認することが必要です。在留資格で認められる範囲を超えた業務に従事させた場合、雇用主は不法就労助…
2025.10.28
続きを見る »
-
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を雇用することはできますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人でも、一定の条件を満たせば雇用することが可能です。主な条件は「資格外活動許可」を取得していることです。
解説
「家族滞在」は本来、就労を目的とした在留資格ではありませんが、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ればアルバイトやパートなど、週28時間以内の範囲で働くことができます。
資格外活動許可がない状態で就労させると、不法就労となり、雇用主の責任が問われることがありますので、必ず許可の有無を確認する必要があります。
フルタイム雇用の場合
週28時間を超えるフルタイム勤務や正社員として雇用したい場合は、在留資格…
2025.10.28
続きを見る »
弁護士からの回答
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人でも、一定の条件を満たせば雇用することが可能です。主な条件は「資格外活動許可」を取得していることです。
解説
「家族滞在」は本来、就労を目的とした在留資格ではありませんが、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ればアルバイトやパートなど、週28時間以内の範囲で働くことができます。
資格外活動許可がない状態で就労させると、不法就労となり、雇用主の責任が問われることがありますので、必ず許可の有無を確認する必要があります。
フルタイム雇用の場合
週28時間を超えるフルタイム勤務や正社員として雇用したい場合は、在留資格…
2025.10.28
続きを見る »
-
在留資格の変更申請中に、元の在留資格の期限が切れたらどうなりますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
在留資格の変更申請を出していて、元の在留資格の期限が切れた場合でも、申請自体が期限内(在留期間満了日まで)に提出されていれば「特例期間」と呼ばれる猶予が認められ、最大2ヶ月間または結果が出るまでの間は引き続き日本に適法に滞在できます。この間は不法滞在にはなりません。
在留カード自体に記載された有効期限が過ぎていても、特例期間中はカード裏面(申請時に記載する場合)やオンライン申請履歴などを用いて、適法滞在中であることが確認可能です。
ただし、申請が遅れた場合や、特例期間を過ぎてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となり、強制退去などの重大なリスクが発生します…
2025.10.28
続きを見る »
弁護士からの回答
在留資格の変更申請を出していて、元の在留資格の期限が切れた場合でも、申請自体が期限内(在留期間満了日まで)に提出されていれば「特例期間」と呼ばれる猶予が認められ、最大2ヶ月間または結果が出るまでの間は引き続き日本に適法に滞在できます。この間は不法滞在にはなりません。
在留カード自体に記載された有効期限が過ぎていても、特例期間中はカード裏面(申請時に記載する場合)やオンライン申請履歴などを用いて、適法滞在中であることが確認可能です。
ただし、申請が遅れた場合や、特例期間を過ぎてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となり、強制退去などの重大なリスクが発生します…
2025.10.28
続きを見る »
-
外国人社員を雇用したら母国の長期休暇に合わせた休暇の付与は必須ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
外国人社員に対して母国の長期休暇(例:旧正月、クリスマス等)と同じ時期に特別休暇を「必ず」付与する義務はありません。日本国内で雇用される外国人も、日本人と同じく「労働基準法」に基づく休暇取得(年次有給休暇、法定休暇等)が原則です。
解説
年次有給休暇や法定休暇の付与は外国人にも平等に行われ、日本人と同じ扱いとなります。
外国人社員が母国の長期休暇時期に合わせて休む場合、「有給休暇」を利用して取得する運用が一般的です。
企業側が独自に「一時帰国休暇」や「母国祝祭日休暇」等の特別休暇を就業規則等で設けることは自由ですが、法的義務ではなく会社ごとの任意です。
…
2025.10.28
続きを見る »
弁護士からの回答
外国人社員に対して母国の長期休暇(例:旧正月、クリスマス等)と同じ時期に特別休暇を「必ず」付与する義務はありません。日本国内で雇用される外国人も、日本人と同じく「労働基準法」に基づく休暇取得(年次有給休暇、法定休暇等)が原則です。
解説
年次有給休暇や法定休暇の付与は外国人にも平等に行われ、日本人と同じ扱いとなります。
外国人社員が母国の長期休暇時期に合わせて休む場合、「有給休暇」を利用して取得する運用が一般的です。
企業側が独自に「一時帰国休暇」や「母国祝祭日休暇」等の特別休暇を就業規則等で設けることは自由ですが、法的義務ではなく会社ごとの任意です。
…
2025.10.28
続きを見る »
-
外国人社員の社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険は日本人とどう違いますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
外国人社員も日本人社員とほぼ同様に、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入が義務付けられています。国籍や在留資格による加入・手続き上の違いは基本的にありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務・適用範囲
主にフルタイムや週30時間以上勤務、または正社員の所定労働時間の4分の3以上働く外国人には、健康保険・厚生年金ともに加入義務があります。
雇用期間が2ヶ月超見込みの場合も対象です。2ヶ月未満で終了が明らかな雇用は適用外となります。
技能実習生や特定技能などの資格保持者も、一般社員と同じ基準で判断されます。
社会保障協定
日本…
2025.10.28
続きを見る »
弁護士からの回答
外国人社員も日本人社員とほぼ同様に、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入が義務付けられています。国籍や在留資格による加入・手続き上の違いは基本的にありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務・適用範囲
主にフルタイムや週30時間以上勤務、または正社員の所定労働時間の4分の3以上働く外国人には、健康保険・厚生年金ともに加入義務があります。
雇用期間が2ヶ月超見込みの場合も対象です。2ヶ月未満で終了が明らかな雇用は適用外となります。
技能実習生や特定技能などの資格保持者も、一般社員と同じ基準で判断されます。
社会保障協定
日本…
2025.10.28
続きを見る »
-
在留カードを従業員がなくしてしまったらどうしたら良いですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
従業員が在留カードを紛失した場合、以下の手順で対応します。これは、どの在留資格でも共通です。
①警察への紛失届提出
すぐに最寄りの警察署または交番へ行き「遺失届」または盗難であれば「盗難届」を出し、受理証明書または受理番号を取得します。
②入管で再交付申請
管轄する出入国在留管理局で、再交付申請を行います。紛失届の証明書類、申請書、顔写真、パスポート(ある場合)を持参し、手続きします。
申請は「紛失・盗難の日から14日以内」に行わなければなりません。
③職場等への報告
勤務先や学校など身分証…
2025.10.28
続きを見る »
弁護士からの回答
従業員が在留カードを紛失した場合、以下の手順で対応します。これは、どの在留資格でも共通です。
①警察への紛失届提出
すぐに最寄りの警察署または交番へ行き「遺失届」または盗難であれば「盗難届」を出し、受理証明書または受理番号を取得します。
②入管で再交付申請
管轄する出入国在留管理局で、再交付申請を行います。紛失届の証明書類、申請書、顔写真、パスポート(ある場合)を持参し、手続きします。
申請は「紛失・盗難の日から14日以内」に行わなければなりません。
③職場等への報告
勤務先や学校など身分証…
2025.10.28
続きを見る »
-
ワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人を雇用することはできますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
ワーキングホリデーの在留資格(特定活動)を持つ外国人は、日本国内で雇用することが可能です。就業に関する制限は基本的にありませんので、雇用形態もアルバイト・契約社員・正社員・派遣など自由に選択できます。ただし、主な目的は「休暇・観光」であり、在留期間は原則1年までです。
雇用時のポイントと注意事項
在留期間を超えて雇用することはできません。不法就労となるため、在留カードやパスポートを必ず確認してください。
所得税率は一律20.42%が適用されます(日本人の累進課税と異なります)。
社会保険や雇用保険の適用条件も、日本人と基本的に同じですが、来日の…
2025.10.27
続きを見る »
弁護士からの回答
ワーキングホリデーの在留資格(特定活動)を持つ外国人は、日本国内で雇用することが可能です。就業に関する制限は基本的にありませんので、雇用形態もアルバイト・契約社員・正社員・派遣など自由に選択できます。ただし、主な目的は「休暇・観光」であり、在留期間は原則1年までです。
雇用時のポイントと注意事項
在留期間を超えて雇用することはできません。不法就労となるため、在留カードやパスポートを必ず確認してください。
所得税率は一律20.42%が適用されます(日本人の累進課税と異なります)。
社会保険や雇用保険の適用条件も、日本人と基本的に同じですが、来日の…
2025.10.27
続きを見る »
-
育成就労制度が始まると何が変わるのですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
 弁護士からの回答
育成就労制度が開始されることで、「技能実習制度」が廃止され、外国人労働者の受け入れに関する目的・運用・権利保護など多くの点が大きく変わります。
主な変更点
制度目的の転換
国際貢献や技能移転ではなく、日本国内の「人材育成・人材確保」が制度の目的となります。
外国人労働者の権利保護強化
本人の意向による転職(同業種内の転籍)が可能になり、不適切な労働環境への対応がしやすくなります。
在留資格の新設
「技能実習」ではなく「育成就労」という新しい在留資格が導入されます。育成フェーズ(最長3年)後は特定技能1号等への円滑な移行が制度上想定されます。 …
2025.10.27
続きを見る »
弁護士からの回答
育成就労制度が開始されることで、「技能実習制度」が廃止され、外国人労働者の受け入れに関する目的・運用・権利保護など多くの点が大きく変わります。
主な変更点
制度目的の転換
国際貢献や技能移転ではなく、日本国内の「人材育成・人材確保」が制度の目的となります。
外国人労働者の権利保護強化
本人の意向による転職(同業種内の転籍)が可能になり、不適切な労働環境への対応がしやすくなります。
在留資格の新設
「技能実習」ではなく「育成就労」という新しい在留資格が導入されます。育成フェーズ(最長3年)後は特定技能1号等への円滑な移行が制度上想定されます。 …
2025.10.27
続きを見る »
新着情報